服部孫四郎著の願立剣術物語を現代語訳しました。こちらのページに掲載している現代語訳は本サイト(Memorandum)が独自に翻訳・編集したものです。
もともと武術や格闘技が好きで、以前から著名な武術の伝書『願立剣術物語』を読んでみたいと思っていました。実際に読んでみると、期待通り素晴らしい内容で、目から鱗が落ちるようなことばかりでした。ただし、現代の考え方や体の使い方、動きとは大きく異なる部分も多く、人によっては受け入れにくいかもしれません。
繰り返しになりますが、この現代語訳はあくまでも私個人の解釈をメモ書きとして残したものです。専門家や学術的な見解とは異なる解釈や誤りが含まれる可能性がある点、あらかじめご了承下さい。
一
伝えられてきたのは流れる水のように、少しの間も止まることのない剣術だ。
たとえば月日が移り変わっていくように、草花が芽を出すように、わずかな時間も止まる事がない。
しかしながら敵が勢いよく打つのに合わせて反撃しようとすると、敵はそれを察知しすぐに打つの止めてしまう。そういった敵との駆け引き、虚実に惑わされてはいけないと分かっていても、心がそれに囚われこちらの動きも止まってしまう。
この剣術はそういった心や動きの滞りを剥がし落とした、玉のようなものだと言える。
二
心は満ち満ちた水のようなものである。
水は自ら動こうとせず、心もまた自ら動かない。 水は草木に従って静かに引かれていくのである。
たとえると、敵は流れてくる水を防ぐ盾のようなものだ。
この盾にわずかでも穴があれば、水は自然とそこから漏れ入っていく。
敵の構えに隙がなければ、水は行き渡る場所がなく、満ち満ちたまま湛えられた状態になる。
敵がかき退けようかき退けようとしても、水はその状況に応じて自由に変化するものなのだ。
三
伝えられた剣術は何か特別なものではなく、怪我や不調の原因となる体の歪みや無理な動き、硬い動きなどの病を身体全体から削り落としたものだ。幾度となくその原因を見つけ出し、執着している心の偏りや怒りといった感情を打ち砕き、意識的な動きから無意識になり、ただ何の問題もない、本来の自然な身体に戻った。
師が弟子の武術における欠点や不調をよく理解し、動きの滞りや恐怖を感じる箇所をあたかも我が身のことのように明確に理解し、その弟子の欠点を改めることができるのは、師も弟子と同じように苦しみ、そしてそれを克服した経験をもとに弟子を直し導いているからである。
四
玉のきよらかさというのはどこにも留まることなく滑らかに動き続けることで、下り坂を走るのに似ている。坂が急であれば玉は自ら走っているのでなく、ただ勢いに任せて転げ落ちているにすぎない。
心がこのように焦っている時は、玉が転げ落ちているのを「走っている」と錯覚し、右往左往してしまう。
何か一つでも余計な乱れが生じて玉に角ができると、そこが敵にとって格好の的となる。弓の名人はその角を的確に撃ち落とす。もし玉に角がなく滑らかに転がっていれば狙いどころがなく、攻撃の的を定めることができない。
五
敵に面向かうとは、敵を自ら探し向かっていくことではない。
敵を探そうとすれば、心に余計な乱れが生じてしまう。
自分の心が自然に向かう先があり、その心を深く誠実に受け止める事こそが重要なのだ。
玉のような心であれば、周囲の状況が自然と心に映り込む。あらゆる方向をよく見通し、あらゆる場所が明確に見え、迷いや滞りが起きる事がない。
そして雑念が無く内面が清らであれば、いかなる状況の変化にも自在に対処できる。
けれどもいざ敵と向かい合うと敵が先手を取り、こちらが後手になり、敵の思惑や動きに引き摺られてしまう。
この点は非常に紛らわしく、玉心というのは理解し難い。
たとえば月の光が差し込む戸を開ける者がいる。この時、「戸を開ける」のと「光が入ってくる」のは、どちらが先でどちらが後と言えるだろうか。
「玉心があらゆる方向に通じている」というのは、月の光が差す場所を選ばず、あまねく行き渡るのと同じ事だ。
戸を開けるというのはすなわち敵と対峙する状況であり、どうしてそこに先手・後手などという区別があるだろうか。
六
剣は円を描く物で、一丈五尺を廻りながら落ちる。
心の働きに乗り、目に映る敵の打ちに引き摺られることなく受け開きできれば、剣がこちらに届く前に攻撃を外すことができるだろう。
けれども敵が動くのを待ち、目に映ってから躱そうとする心では、一丈五尺を落ちる間少しも外す事はできないだろう。
心はただ玉のように澄み切っているべきである。
心の玉が巡るその一瞬のうちに、動揺し病が生じることがある。
そうするとある時は焦って前に出すぎ、ある時はためらいながら足を踏み出したり、体をひねったりしてしまう。これでは本来丸くあるべき動きに「角」が生じ、相手に打ち砕かれてしまうぞ。
また別の病として、恐怖で身を引き、肩をすくめて萎縮し、力任せに相手の太刀を押さえつけようとしたり、手首が力みタイミングが早くなったり遅れたりと動きがつかえてしまうことがある。こうなると丸くあるべき心や動きに「窪み」ができ、本来あるべき姿とはかけ離れた状態になってしまう。
七
体は天地に吊り下がり、絶妙なバランスの上に成り立っている。頭、頸、胴体、両手、両足ーー体のどこかが偏り片側だけが吊られることがないように心がけなければならない。
たとえばうつむいたり、逆に上を向きすぎたり、腰をひねって腹を突き出たり、力んで肩を上げたり、足を使い大股で歩いたり、或いは踏ん張ったり、これらは「片吊り」が生じた状態である。
何かに執着するとそれに心身が囚われ、動きは氷のように固まってしまう。そうなると水のように自由に動く本来の理を知ることができない。
もし、本当に水のような自由さを知りたいのであれば、まず、体の力みや偏りなど全ての病を取り除くことだ。そして片吊りのない、ありのままの体を自分の基準として定め、それを絶対的な物差しとしなさい。
その上で手の上げ下げや、前後左右全ての動きが体の内に一切の滞りなく行えるよう、その感覚を骨の髄まで染み込ませなければならない。
これは、火の熱さは肌に触れて知り、食材は味わって知るのと同じことだ。
頭で理屈をこねくり回し、言葉にして理解しようとするな。ただひたすら教えの道に打ち込みなさい。
理というものは、後から自ずとついてくるものだ。
八
「引導」ということは極めて重要である。
雑念を持たず、師の教えに従って導かれることを言う。
五体のうち、右手は全身の動きを先導する「前手」である。この働きこそが引導なのだ。
心の向かう方に前手をすっと片吊りなく出せば、その勢いに引かれて足も動き、体全体もついてくる。
まるで像に影が寄り添うように、自然と全体が連なって動く。
水に浮かんだ舟を押すと舟全体が動くように、一方動かせば四方動かないということはない。
すべてが同時に、滑らかに、一体となって動くのだ。
たとえ百万人、千万人の兵がいたとしても、大将一人の命令に従わなければ勝利はあり得ない。
それはたった一人の戦いでも同じことである。人の五体はただ一つの心に従って動き、手足も前後左右の動きも、すべては心の働きによって成り立つ。
無数の動きがあるように見えても、そのすべては、「一つの心」から発しており、最終的にはすべて心に帰着するのだ。一人と戦うのも、千万人を相手にするような大戦でさえも、その本質は「ただ一つの心」にある。
大勢を指揮するには自分の手足と同じように、巧みな工夫と統率が必要である。
一対一の立ち合いだけに役立つ術を剣術と思い込んでいるようでは達人とは言えない。
たとえば平家物語や古の戦の記録をいくら読み漁り、書物で軍法を多く知ったとしても、それを軍法と呼ぶべきではない。書物の知識だけで己の弱さや欲望に勝てる者はほとんどいない。
敵に勝つことだけを求める者は終わりない争いに身を置くことになる――古来そう言われてきたのだ。
自らの身体一つを自在に操るということは、大軍を思いのままに動かすことと全く同じ心得だと知るべきである。
手が二本、足が二本、そして胴体を合わせて五つである。
五人組を一つの単位として、そこから二十五人で一隊、五十人で中隊、それが五つで一軍と編成されていく。
そのすべては大将一人の命令に従わないと成立しない。
私たちの五体も同じで、それぞれが勝手に動き、心の命令に従わなければ必ず敗北する。
五体のうちで左右の動きがばらばらになり、特に左手が指示に従わず勝手に動く事は大いなる間違いである。
あらかじめ両手を同時に使う稽古を積むのは、左右が別々に動いてしまわないようにするためだ。
訓練が不十分なまま右手だけで習得してしまうと、右手だけがうまく動くようになり、左半身は取り残されてしまう。
そうなると動きに前後のズレが生じて、調和が取れた円の動きからかけ離れてしまう。
九
「三拍子」という病がある。
三拍子とは敵が動き、目で見て、心を通さず敵の動きに引き摺られそのまま手先で動いてしまうことだ。相手の動きや表情に惑わされたり、敵の打ち込みを見てから打ち返したり、あるいは受けたり外したりすることである。
こうした動きはすべて三拍子と呼ばれ、結果として常に敵の後を追うことになる。
目に頼り、敵が動いたのを見てから反応するようではいけない。 この三拍子という病を取り除き、怠ることなく自らの身一つを自在に使えるようになれば無病の身となり、太刀を構えた瞬間に敵の打ち込みも突きもすべて見通せ、的確に対処できるようになる。
十
肩の付け根の使い方は、弓を射るのに似ている。
ただし、弓が体を横に向ける左構えであるのに対し、これは体を正面に向ける前構えという違いがある。
先ず、ありのままの自然な構えで楽に立ち、首筋をしっかり伸ばす。
そして肩は根本から力を抜いて落とし下げ、そこから前方へ押し出すような意識で両手を適切に伸ばす。その腕はまるで木製定規を継ぎ足して一本にしたかのように、肩から手先まで骨の連なりが乱れ無いようにする。
また、「手を伸ばす」には「延ばす」と「及ぼす」という、全く異なる動きがある。
敵に届かせようという外向きの意識だけで体や手を伸ばす「及ぼす」動きは、身体の外側だけを使った動きである。
そうではなく、身体の内側からしっかりと滞りなく伸ばすのだ。
全体をしっかり伸ばせば自然と相手に届く。
心も身体も手も所作もすべてにおいて一切の緩みなく、充実し気が満ちた本質的な剣術を「性の位」と言うのだ。
たとえば、澄み切った鏡のように敵の動きが我が心の鏡に映ると、 敵の所作もこちらの所作もひとしく明晰となり、自然と正しい動きになる。言葉を発しようと思えば意識しなくても舌が自由に動いて言葉が出るように、 あるいは長い竹の根元を少し動かすだけで先端の葉まで一斉に動くように、 心と身体が一体となり滞りなく動くのである。
十一
身の備え太刀構えは、なみなみと水を注いだ器を敬うように大切に持つ心構えでなければならない。
むやみに太刀を振り回したり、身体を歪めたりすると、その隙を敵は見逃さずに打ち込んでくる。
敵を押さえたり、受けたり、無理にかわそうとすることも非常に悪い。
基本的に太刀の先から動かすことはせず、腕(かいな)だけを使うのだ。
前後左右、上下全ての動きが丸く円滑でその勢いが続く様は、あたかも名人が文字を書くようなものである。
書の名人が文字を書くとき、頭で考えた理屈を筆先だけで書いたりするものではないように見える。
十二
敵が「ここを打とう」と狙いを定め「えいっ」と打ってくる動きは、的を狙って投げる石のようなものだ。しかし、それは自然な動きとはいえず、生き物に対するものではない。まるで根のない草のようなものだ。これは、下手な射手がただ的だけを見て矢を放つのと同じで、そのやり方は本質から外れた偽物である。
弓術の真髄とは静止している的を見て放つのではなく、自分の内にある定まったところから放つのである。下手な射手が的を狙うようなものではなく、常に動き続ける「生きた的」であり、止まっている物ではない。それは道を行く月の影のように、常に動いているのだ。
一つの心が全身に満ち満ちて、自然な流れが一切途切れない状態になると、敵がほんのわずかでも動いたその瞬間に自分と相手の区別もなく、その意図がこちらの心に映し出される。だから敵が狙おうとしたその的を、自分でも意識しないうちに外してしまうのだ。
心は少しも動揺しないが内に満ちた勢いがあるため、たとえ相手に打たれてもその勢いが砕けることはなく、押さえつけようとしても動きが滞ることはない。
十三
太刀を握る手の内の事。
両方の手のひらを向かい合わせて持つその形は、仏像が結ぶ印相のようでなければならない。
まず最も大切なことは、太刀は手のひらの小指側を意識して柔らかく握り、その印相のように形作った手の形を崩さずにそのまま相手に向けて構え、肩の力を抜いて落とし、自己流の小細工などを働かせず、師から教わった正しい教えをただひたすらに守り、実践することである。
太刀を乱雑に棟側から押さえ付けるように握ったり、左右で手の力の入れ方が違ったり、手の内をすぼませたり、一重身のような構えで相手に備えたりすると、体はゆがみ、肩に力が入り、心が浮つき下半身が軽くなりと、良いことは何もない。
「一重身」という構えは当流に存在しない。上半身は状況によって一重身になることもあるが、腰から下が相手に向いていなければ前へ進むことなどできず、ねじれた不自然な姿勢になってしまう。
十四
舞の動きが終わりまで謡の心とぴたりと合っているのを見て、「よく思い入れが深い」と言う人がいる。
この「思い入れ」というものを剣術に例えて考えてみる。
「敵を斬ってやろう」と意気込むことでもなければ、「斬られてはなるものか」と思うことでもない。
身を捨てようと、身を守ろうと、力を込めようと、怒ろうと、喜ぼうと、あるいは死んだ気で覚悟を決めようと、そういった心構えはいざという時には少しも頼りにならないもののように見える。
しかしながらたとえ偽物であっても、死んだ気で覚悟を決めるのはどうしようもない臆病者でいるよりましである。
それでは「思い切る」とは一体どういうことか。
生死というのは天命によって自ずと定まっているのだから、前に進んだからといって必ず死ぬわけではなく、退いたからといって必ず生き延びるわけでもない。 生きとし生けるものの生死にはそれぞれ定めがあると分かっていれば、死すべき時も退くべき時も静かに受け入れることができる。生きる事や死ぬ事に囚われ、見せかけだけ思い切ったように振る舞う人を世間では「覚悟がある人」と言っている。
能の名人も同じ事で、 平生から舞の拍子に思いを込め、寝ても覚めても怠ることのない志を抱き研鑽を積み重ねる。その不断の心がやがて「何ものにも囚われない真の境地」に至らせるのである。その時こそ、人は「思い入れが深い素晴らしい芸」と言うべきではないか。
「太閤記」にこう記されている。
金春大夫が能の稽古を始めるとき、 まずは身体に染みついた悪い癖を取り除くことから始めるという。 ほんの少しでも袖の振り方に不自然さがあれば、 それが良くなるまで徹底して稽古を重ねる。
良い所を無理に強調したり求めたりするのではなく、 ただ謡の理にかなうよう身につけていく。
大いに清らかに、そして謙虚に日々の稽古を積み重ねていくことで、「自然の美」に至ることを希うのである。
学問においてもまた同じで、 悪しき心を取り除けば自然と善き心が満ちてくると説かれている。
十五
万方一つと云う事。
この世に存在するありとあらゆるものは、すべて「自分自身のただ一つの心」に他ならない。
それは、月(真理)を指し示す指のようなものである。月を指し示す指も、その先にある月も、結局は自分の心なのだ。
これは剣術においても同じである。自分の心に従わず、敵の動きに引き摺られ、その場しのぎで応じようとするのは、東西南北を知らず、雲に目印をつけて進もうとするようなものだ。
その愚かさは舟から剣を水中に落とした際、舟の縁に「ここから落ちた」と印を刻むようなものである。
限りなく広がるのは「謀の道」だ。
敵は様々に変化し飛び回り混乱させようとしてくるが、自分の体の基準をよく計り、滞りの原因となる自分自身の病を全て取り除き、一筋に習いの道を行く事が重要である。
手足を勝手に動かし、体をねじり、顔をゆがめるような戦い方は、まるで腹の中にそれぞれ別々の者がいて、手を使う者は手だけ、足を使う者は足だけ、身をねじる者はねじることだけを行っているようなものだ。それでは「万方これ一つ」という境地に至らない。
大公望はこう言っている。
「およそ兵法の道では統一されている事が何より優れている。統一されていれば自在に進み、自在に退くことができる。」と。
十六
どのような兵法書にも、「敵から主導権を奪った時は勝ち、奪われれば負ける。」と書いてある。
しかし、「主導権を奪ってやろう」と意気込むのは良くない。逆に「奪われまい」と守りに入るのも良くない。
ただ、自らの技が正しく一点の曇りもないのであれば、そもそも「奪おう」という意識も生じないし、相手に「奪われる」ような隙も生じない。
それは、「朝日は星の光を侵そうとしなくても、昇れば自然とすべての星の光は消されてしまう」という古い言葉が示す通りである。
楠兵庫(楠木正成)が記したものにも、
「勝敗は兵力の多い少ないによって決まるのではない。敵の主導権を奪った方が勝ち、敵に主導権を奪われた方が負ける。」と書かれている。
このことはよくよく心に留めておくべきことである。
十七
敵の構えが正眼であろうと、攻撃的な陽の構えであろうと、あるいは守備的な陰の構えであろうと、どのような構えであったとしてもそれに対応しようなどと考ず、ただ敵と向き合ったその方向に向かって「ことわり(理)の車」を飛ばすのである。
敵が抑え込もうとしたり、あるいはその車を捕まえようとするかもしれないが、その車は水が流れ火が燃え広がるような自然の理そのものの天性の車輪なのだから、敵が押さえようと考える暇さえなく、車は瞬時に通り過ぎていく。それでも押さえようとする者は、たちまち車輪の下敷きとなって砕かれてしまうだろう。
これを斬りつけようとしても、飛ぶ鳥の影を斬りつけるようなもので、決して捉えることはできない。
はね除けようとしても満々とたたえられた水、 離れようとしても水、払いのけようとしても水でどうしようもできない。
静かに慎重に相手をしようとしても、それは刃に触れるようなもので傷を負うことになる。
なんと奥深い境地だろうか。
これこそが「吹毛利剣(毛を吹いても切れるほどの鋭さを持つ剣)」である。
罪ある者は自らの過ちによって滅び、己の咎を知る。
罪なき者はたとえ十万の敵に囲まれ八方から刃が迫ろうとも、真に善なる者は苦しむことなくただ一人立つことができる。
十八
字とは本来、清々しく伸びやかに書くものだ。
敵の表情や気配といった表面的な動きに囚われると、相手の攻撃が当たってしまう。なぜなら外側の様子ばかり意識し、自身を省みることができていないからだ。自身を省みれていないという事は、「内外一杯に意識が行き渡っていない」ということなのだ。眼と心と身が一致し内外ともに明らかで隙が無くなれば、こちらが特別な動作をせずとも討つべき場所がなく、ただ独り進むだけである。
この教えの根本は「一」という字に集約される。
書の道においても、小手先で筆の先をこねくり回すように動かすものではないはずだ。
たとえば「一」という字を引くときに筆と手と心が一致していなければ、心が取り残されたり先走ったりしてしまい、そうして書かれた文字は「死に文字」となってしまう。
しかし、筆と手と心が完全に一致し「今、この一瞬」に集中して書く時には、ただ「一」の線を引いただけでも、あるいは墨をつけただけであってもそのすべてに勢いがみなぎる。そのような書を書ける者を名人と呼ぶのだ。
文字の形そのものに本質的な良し悪しはないように見える。
十九
ある猟師の話にこういうものがある。
「小さな鳥は射止めやすいが、大きな鹿は射止めにくい」と。
考えるにそれは鹿が絶え間なく歩き続けていて、「ここだ」と定めて狙えるような留まることがなく、撃ちにくいのであろう。
一方小鳥はこの枝からあの枝へと飛び移り、必ず留まる場所がある。
だから小さいながらも小鳥は射止めやすいのだろう。
二十
心が満ち満ちて明らかな状態になれば、あらゆる方向に意識が行き渡り、何一つ執着や囚われるもののない安らかな境地となる。
この「安らかな境地」こそ、十方へ通じる心の玉なのだ。
しかしひとたび動きだせば、向かうべき方向に玉は自然と備わり走り出す。
敵が速やかに攻めてくるときには、下り坂を走るよう勢いよく転がり出す。
静かな時は坂をすべるように滑らかに転がるのだ。
たとえれば、草木は感情や思考はないけれども、春が来て梅の花が自然と咲くようなものである。
心の玉は形がない「空」を束ねて玉としているので、あらゆる方向を滞りなく見通し、自由自在に振る舞える。
たとえ目で見て耳で聞いたことであっても、それは「空の玉」を動かすことであり、状況に応じて自然と動くその様は、蓮の葉の上で丸くなった水滴が滑らかに転がるようなものである。
二十一
剣体と成す事。
草木一本に至るまで、それぞれが理にかなった自然な姿で立っており、それはまさに剣体を備えていると言える。
元来剣術で剣を甲冑としてこの体を包み敵の中へ入っていくには、剣体とならなければ成す事はできない。
たとえば相手が力任せに打ち込んできたのに対し、無理に押し返そうと力んだり、受け止めようとして相手に組み付いたりすれば、かえって自分自身の剣体を崩してしまい、一撃で打ち負かされてしまうだろう。
たとえ重い一撃が上から落ちかかってきたとしても、力んで余計な動きをすることなく、ただそのまま自分の剣体を保ちスッと立ち上がれば、重い一撃であってもひとりでに落ちていき、自分は何事もなく道を進むことができる。
二十二
「気」が「心」に従うのは曇りがなく良い状態である。
逆に「心」が「気」に引き摺られてしまうのは悪い状態だ。
心とは例えるならば鏡のようなものである。
気とは全身に満ちている根源的な生命力のことである。
この気が心に従う時というのは、色も形もなく澄み切っている鏡に、あらゆるものがそのまま映り込んでくるようなものだ。
しかも、鏡自体は少しも動揺せずあらゆる物の形が一つ残らず浮かび上がる。心も同様に少しも揺れ動くことなく、敵の動きの善し悪しすべてが映し出される。
たとえ何か気になるものを目で見て耳で聞いて一時的に気がそちらへ反応したとしても、気に心が引き摺られなければ、動揺したり、気持ちが曇りやる気を失ったり、暗くなったりすることはない。
だからこそ乱れそうになった気も、結果として心に従うことになるのだ。
これは修行をする上で大切な心得である。
「心は気に引き摺られてはならない」と意識すること自体が、すでに心が気に引き摺られているのだ。結局のところ、「心」と言っても、「気」と言っても、あるいは「性(万物の本質)」と言っても、様々な名前で呼ばれてはいるが、その根本は一つである。
では「気に心が引かれる」とはどういうことか。敵の太刀がひらりと動いたのを見てそれに釘付けになったり、あるいは怒りが湧いたり、あるいは恐怖心に襲われたり、勝ちたいという欲にとらわれたり、表の動きや裏の思惑に固執したり、敵の構えに引き込まれたりするのが気に心が引き摺られた状態であり、その事に心が留まってしまう。
こうなると本来あるべき心は背後に退き、自分の前面は留守となる。鏡のように澄んでいた心には色や形が映り込み、周囲の状況が曇って見えなくなってしまうのだ。
二十三
およそ世の中のあらゆる物事は、理と所作の二つから成り立っている。
勝負における理を深く理解し、それが明確に自分の心に染み渡り、完全に自分のものとなった状態を「本理」と言う。
そしてその理の通りに実際の所作が少しも異なることなく行われることを、「本理」とも、「本所作」とも言うのである。
もし理と所作が分離してしまうのであれば、それは理が心に徹底されておらず、その極致に至っていないからに他ならない。
「理屈はよく分かったけれど、実際にはできない」というのは一体どういうことか。
それは、理が自分の中で熟しておらず、ただ他人から教わった理屈を借りているだけで、まだ自分のものになっていないからである。
静かに心の中で思索してみれば納得がいき理解できたように思えるが、しかしいざ実際に動いてみると理と所作がバラバラになってしまう。そのように理と異なる部分こそが「無理」な動きなのである。
そしてその無理が生じたところを相手に打たれてしまうのだ。
修行を積み重ねていくとやがて理と所作が一体となり、もはや二つに分けることができない境地に至る。 それは「真の理」とも「真の所作」とも、あるいは「明鏡」にもたとえられる。
この境地に達すると、あれこれと分別する事も知恵を絞る必要もなくなり、 立っていても座っていても何をしていても道理にかなっており、 動きには一切の乱れがなく、自由自在に振る舞えるようになる。
一方で所作は巧みにこなせても、その背後にある道理が腑に落ちていない人は、 たとえ所作が上手く見えてもまだ自分のものにはなっていない。 それは他人から借り受けた所作にすぎず、 たまたま上手くいくことがあったとしてもかえって大きな失敗を招くことになるのだ。
二十四
「事」と「理」は別々のものではない。
理に基づいて事象が起こるのである。
「理の修行」と「所作の修行」、どちらを先に学ぶべきかと問われれば、 先ずすべての根本である「理の修行」で道理をよく理解し、その理を本当に自分のものとして明らかにしているかどうかを「所作の修行」で実際に確かめるのである。
理が前になることを否定するわけではないが、ここで言う理とは、言葉で語られる理屈のことではなく、何かを行おうと思えば足がすらすらと動くように、身体が自然と自由に動くはたらきのことである。
技の道において理ばかりにこだわってしまうと、理だけが先立って実際には役に立たなくなる。
まずは技から道理を探り練り上げていき、その道理が熟しているか未熟かを何度も何度も所作として試してみる。
そのとき動きがまだ未熟であれば、道理もまた未熟であると心得るべきである。
所作と道理が共に熟してくればやがて一つとなり、 立っていても、座っていても、眠っていても、目覚めていても、 心と技が離れることなく不思議なほど自然な働きが現れる。そうなると「勝とう」と意識することもなく知らぬ間に勝ってしまい、 言葉にも筆にも表しがたい境地となる。
そのときには何ひとつ恐れることもなく、 迷いや疑いは消え去り、 槍や薙刀のような長物でも短刀や小太刀のような短物でも自由自在に扱えるようになるのだ。
二十五
敵の表情や駆け引き、虚実に心が乱れてしまうのは、実がともなっていない証拠である。自分の心に正直を立てず、そういった表裏の思いを自ら抱いているから、敵の表裏に引きずられるのだ。まずは自分の心から表裏を取り去り、一つの法を大切に守り抜かなければならない。
「妙(すぐれたはたらき)は法(天地自然の理)の中にある」と言われている。その法をしっかりと励むとき、妙はおのずからあらわれるのである。
「表裏に執着するな」とたしなめる心さえ、すでに表裏にとらわれている。
師から授かった一法をよく勤め励むならば、どうして表裏の思いが起こるだろうか。
そこには生死の思いすら生じない。
二十六
恐れの気持ちが出るのは、自分の中に未熟さや欠点があるからだ。
恐れがあると心がその欠点にとらわれ、ますます自分の状態は悪くなる。
結局のところ、それは稽古が足りないことと、教えに対して素直になれず、心に迷いや疑いを抱いているからだ。
教えに素直に従うというのは、言うほど簡単なものではない。
だが、もし余計な疑念を持たずに師の教えにまっすぐ入っていくならば、恐れもなく、怒りも生じない。
敵がどんな構えをしていようとも、自分を打ってくるということに変わりはない。
自分が敵に打たれる位置に入らなければ、敵の攻撃は当たらない。
二十七
手は心が及ぶところへ寸分違わず動くものだから、まず心が宿る体をしっかり整えることが重要である。
心は水のようなものだ。水は器の形に従う。器(体)がしっかりしていれば、水(心)は動揺せず、静かに自然と安定する。
敵がこの器に強く当たってくれば強く動き、弱く当たってくれば弱く動くだけだ。
孫子曰く
「そもそも兵のあり方は水に似ている。水が高い所から低い所へ流れるように、兵は防御が固い所を避けて隙のあるところを攻める。
水が地形によって流れを決めるように、兵は敵の状況によって勝利の形を決める。
ゆえに、兵には決まった形はなく、水にも決まった形はない。
上手く敵の状況に応じて変化し、それによって勝利を収める者は神のような存在である。
ゆえに五行(木火土金水)では常に勝るものはなく、四季には一定の場所がなく、日には長短があり、月には満ち欠けがある。」
二十八
ひとたび「はっ」と心がつり合ったならば、その心の働きや動作は最後まで続け、二度と集中を切らしてはならない。
敵の太刀が矢のように襲ってくるときでも、まぶたを閉じ合わせるほどの一瞬の間に心を継ぎ、最初に得た心のつり合いを失わず、太刀先も乱さず、少しも体勢を崩してはならない。
「はっ」と心がつり合ったとき、それは自分自身の夢(迷い、油断)から心を目覚めさせることである。これは決して拍子を合わせることではないし、また敵と力を張り合うことでもない。ただ、己の本性のすみずみにまで行き渡った心の充実を言うのである。
何の理由もなく自然とつり合うことを「つり合い」と呼んでいる。
もし敵の攻めに応じて「はっ」とつり合ったように感じたならば、それは敵によって心が夢から覚まされたのである。
自分の中に独り立つつり合いがなく死に物狂いになっているので、敵の策略に引き込まれ、心を変えてしまうのだ。
二十九
心が「びく、びく」と驚いてしまう悪い癖があるのは、自分が夢(敵の誘導や囮に惑わされること)から覚めずに敵の偽りに引き込まれ、急にその夢から覚めるためだ。
また、心や所作に「カクッ」と段差のような途切れが見えるのは、敵に心が取りついているために、敵がひらりと変化した時、倒れかけた人が杖を外されたように支えを失ってしまうからだ。
自分を押し潰そうと攻撃をしてくる目の前の敵は「悪」である。その悪に心を預け頼ろうとするのは愚かさの極みである。
何度でも戒めるべきはこの迷いだ。
三十
太刀の道を正しく修めることが何よりも大切である。
およそ物事には「はまり」という状態がある。
それは稽古によって自分が到達すべきところまで進み、しっかりと身についている状態を指す。
ただしその状態に満足し、僅かたりとも留まってはならない。
敵が上を打つと見せかけて打たず、半返りして下を打ってくることがある。その時本来自分が行うべきことを止め、途中で半返りして敵が下を打つのに合わせようとするのは、犬が投げられた物を夢中で追いかけ肝心の投げた本人を追いかけないようなもので、表面的な動きにつられているに過ぎず、全く正しい道ではない。
それはその人自身の才覚(小手先の器用さ)によるものだ。
その刹那の間に対応方法を考え、自分の才覚だけで敵の変化に対応することは、神通力を以てしてもできはしない。
ただ自分が行うべき道を正しく実践し、動きが完全に身についていれば、無意識のうちに敵の変化に対応できる。それはまるで左右の手を合わせるかのように何の計らいもなく「はまる」のである。
だからこそ、ひたすら自分がやるべき道を実践し、修める事が重要なのだ。
孫子曰く、
「戦いに巧みな者はまず自分が決して負けない態勢を整え、その上で敵が敗れる状況になるのを待つ。
敗れるのは自分次第であるが、勝てるかどうかは敵次第である。」
三十一
身構え、身体のつり合いの事。
足下は居つかず軽く、膝はふらつきがなく、背筋は通り、腹の内は整え、 下腹には重みを持たせ、腰を据え、肩は力を抜いて落とし、首筋には張りを持たせ、 左右の手は歪みなく自然に伸ばし、右手を前に出しながら、左右の肩のつり合いを保ち、 手の内は何も作為せず、ただ自然なままにしておく。
そして、習った道をそのまま行うことに専念する。
そもそも五体は天地の吊りものである。
五体を吊る頂きは天の天から意識し、足下は地の地に至る。
三十二
本来人の性(根源的な性質)は恐れの気持ちもなく、怒りもなく、疑いもなく、表裏もなく、急ぐことも早まることもなく、強いも弱いもなく、勝ち負けにとらわれることもない。
ただ炎が燃えさかるように、木の枝葉が風にそよぐように、始まりもなく終わりもなく、生きるも死ぬもない。
人もまた自然の理の中にあり、止まることなく移ろいゆく身であるというのに、たった一つの物事を基準に「上か下か」「右か左か」「若いか老いか」「生か死か」「強いか弱いか」「勝つか負けるか」などと執着し、敵を討とう、または討たれまいとする思いに囚われることは、「生を貪り、死を恐れて嘆く心」に他ならない。
これこそ愚かさの極みであり、まさに迷いそのものである。
三十三
歩くときのように常に運ぶ側の足だけが動き、踏みとどまる足は少しも動く事はない。
足運びは軽やかで、足は手に導かれて進み、手は師の導きによって引かれていく。
足と手を同時に動かそうとすれば、手にも「行こうとする心」、足にも「行こうとする心」が生じ、一つであるはずの導きが二つ三つに分かれてしまい、「万方一つ」の理から外れてしまう。
少しでも自ら足を使って運ぼうとする心があれば、その導きは偽りとなり、敵は見抜いて打ち砕いてくるぞ。
そもそも足は「動かぬもの」と知るべきだ。
立つときは立つだけの役割、留まるときは土台の役割である。
手の導きに従って右のつま先が地を離れ、次に左の足が少し出る時、右の足は地に着いている。
踏み換えは常に一つであり、立つ心の及ぶところへ足が運ばれていく。
速やかなときは飛ぶ鳥のように、静かなときは流れる水のように進むが、歩く事は意識しない。
疾く疾くと流れるように淀みなく進む。
三十四
手は車輪のようなものだ。
車輪をまっすぐ押すときは自由自在に動くが、 横から押せばたちまち壊れてしまう。
稽古で習得した正しい動きを自分の太刀が届くところまですらすらと行えば、 敵が攻撃する怒りはこちらの動きとともに砕け落ち、 敵も自らの道を行き、こちらも自らの道を行く事になる。
前へ進む心の車輪が一つ、左右へ動く心の車輪が一つ、 この二つが合わさって四方に動く輪となる。 だからこそ、「玉を転がすような動き」が生まれるのだ。
この輪を回すことが何よりも大切である。
太刀が当たる瞬間に、急にガクッと回そうとするのはよくない。 始まりもなく終わりもない循環のように、途切れることなく動くのである。
心の輪が少し回り始めると、 その末には五尺の輪にもなり、 あるいは五間、百間、千町、万里にも及ぶ輪となる。
「前へ進む車輪が一つ、左右へ動く車輪が一つ」と言えば、 車輪が二つあるように聞こえるかもしれないが、実際には二つではない。 常に自分が前に進む車一つを正しく押せば、左右の動きは自然と備わる。
これができた時、玉の形が分かるのである。
三十五
動きの中で敵の動きを目で追って見るのは「二重のこと」である。
もともと敵は目の前に見えているので、改めて「見よう」とすればそこが隙となり、動きが緩んだものとなってしまう。
そしてその緩みを敵は見逃さず打ち込んで来る。
正しい目付とは、一粒の雨が波紋となって広がるように、霜に置かれた露が滲み渡るように、一点から全体へ意識が広がっている状態をいう。
たとえれば、こちらの岸に露が一つ落ちれば、その波紋(心)が万の岸に広がっていくようなものだ。
三十六
この流派は敵の表情や構え、動きを見てその動きにただ従うわけではないし、まったく従わないわけでもない。
敵の速い動きに合わせようとするのは才覚(小手先の器用さ)に過ぎず、犬が投げられた物を追いかけるようなものだ。
そういうやり方は敵に打たれ、その後を追う事になる。
敵は遠近距離を変え、飛び動き、虚実を織り交ぜながら様々な技を繰り出してくるが、その動きに囚われず、ただ自分の心を正しく澄まし、自分の道を行くことが重要である。
決して「敵を責める」ことをしてはいけない。これは「自分を正していく」道なのだ。
心が弱く敵の動きに心を惑わされ、そこに実があると思い敵に合わせるのは、水に浮かぶ瓢箪を押すようなものだ。
あれを押さえ、これを止め、ここを外し、あそこを受けといった具合に翻弄され、やがて対応への疑念から動きに迷いが出て、これもうまくいかず、あれもうまくいかずと最後には打ち砕かれてしまうだろう。
三十七
兵法において「紀(法則や道理)」というものは極めて大切だ。
速い動きにも紀があり、遅い動きにも紀がある。
もし敵を早く取り押さえようと焦れば、「早く敵を取り押さえなければいけない」と心が働くため、紀から外れた不正確な動きになってしまう。
逆に自分の動きを整えようとゆっくり動けば、敵を追い詰めるのが遅くなり、余計な動作が増えてしまう。
自分の動きが乱れている時は、心が自分の道を見失っているのであり、敵の後を追いかけることになる。
だからこそ、自分自身の道をただ一筋に究めることが重要なのだ。
速くても遅くてもあるいは混乱している状況であっても、その中に「紀」を保ち続けることが兵法の極意である。
三十八
速い動きにも「色(個性や特徴)」があり、遅い動きにも「色」がある。 しかし「性(根源的な性質)」には色も香もない。
自身の速い動きには限界があり、 遅い動きもまた限界がある。
たとえれば、「ここまでが限界だ」と言えば、 その上にはさらに勝るものがいるかもしれず、 「どこまでが限界か」と問えばそれには限りがない。 それは、仮名の「し」の字を引くようなものである。
一、二、三、四、五と数があっても、 もとはすべて「し」の字の流れである。 「し」の字を折り曲げて、一つ二つと数えるのは、 人が勝手に定めた心の働きにすぎない。
縦に引けば「し」の字、横に引けば「一」の字の流れとなる。
この「一」の字から万物が生み出されており、この「一」こそが根本なのだ。
善を求めることもなく、悪を避けることもない。
「柳は緑、花は紅」――ただそのままの姿を上下左右に巡らせたものが技である。
敵が打ってきたときに「はっ」と慌てて対応するようでは、 根本である「一」の字そのままの境地ではない。
ふわりと上へ刀を上げたり、ふわりと下へ下ろしたりするのは、「し」の字を途中で切ってしまうようなもので、「性」の流れを断ち切った死んだ文字である。
上へも下へも脇へもただ上がっていくものではない。
上がるならば、敵を巻き込み下から跳ね上げればよい。
下がるならば、敵を巻き込み上から打ち砕けばよい。
左右も同じだ。
よくよく心得るべき重要な事は、ただ「中央を取る」ことである。
三十九
心を疎かにしてはいけない。
形に影がより添うように、心により添う影が「所作(行動や振る舞い)」である。
最初は心を捉えることが肝心だと理解し、それができた後捉えた心をも手放すのだ。
心が外ばかりに意識していると自分の内面が疎かになる。
まずは自分の内面をよく観察し、心の奥底までしっかりと捉えなさい。
ただし、内面ばかりを意識していると周囲が見えなくなる。内にある心をしっかり捉えたら、それすら執着せずに解き放ちなさい。これを「放心」と言うのだ。
四十
迷った目を頼り、敵の打ち込みを見てからそれに合わせようとするのは、雲に目印をつけるようなもので、全く当てにならない。
まずは自分の構えをしっかり定め、日頃の稽古を十分に積み重ねておけば、かゆいところに手が自然と届くように五体が滞りなく動き、心と体と眼が一体となり、自由に働くようになる。
そうなれば意識せずとも自然に勝利を得ることができるだろう。
日頃の稽古を怠り、行き当たりばったりで敵の姿を見て勝てる勝てないと判断するのは愚かさの極みだ。
四十一
敵と味方の間は大きな川にたとえられる。
川は舟がなければ渡ることができない。
その舟を使って渡る方法こそが、兵法の道である。
舟が自由に進むのは、櫂を左右に動かすからだ。
教えの道を一つ、二つ、三つ、四つ、五つと段階を踏んで進むのは櫂を動かすようものであり、向こう岸へ渡るための手段である。
少しも滞ることなく、波の揺らぎに舟が従う様子に似ている。
水から離れれば舟は自由に動けない。この舟が自由に進むための水が「心」であり、舟は「身体」であり、 櫂は「手足」である。
四十二
手の内や身構え、敵との間合いなどを「これがちょうど良い」「これで勝てる」と心で思うのはすべて誤りである。
良いも悪いも本来そこにはない。
自分の心にこだわり、自分の理屈に囚われ、自分が納得できることが真の道理であるかのように思うものは本理ではなく、私見に過ぎない。
古くからこう言われている。
「道は見ようとして見れるものではない」
「事(現象)は聞こうとして聞けるものではない」
「勝はあらかじめ知ることができない」
四十三
「つり合い」ということについて以前に語り尽くしたとはいえ、これはあらゆることの根本であるため、よく理解しておくべき大切なことだ。
水と火のように、人間もまた互いに打ち消し合う性質によってつり合っている。
鳥や獣も同じである。
鳥が鳥を捕らえることができるのも、鷹が見事な「つり合い」を備えているからである。
人が人に勝つのもつり合いが取れているからであり、獣が獣に勝つのもまたつり合いによるものである。
鳥が空を飛ぶのは翼を広げて風の力を受け、その風とのつり合いを保つからだ。
足のない生き物が地を這うのも、魚が水の中を自在に泳ぐのも、みなつり合いによって成り立っている。
この「つり合い」を失えば、鳥は地に落ち魚は水面に浮かび上がってしまう。
この流派の修行の根本は、「心のつり合い」をもって「体のつり合い」をはかることである。
心・身・眼が一つに調和し、少しの滞りもなければ病のない身体となる。
思い煩うことが無くなれば楽遊より他はない。
これは外に求めて得られるものではなく、自らの内に備わっているものなのだ。
四十四
「移り写す」を理解しようとすれば二つに分かれるように見えるが、本来はひとつの働きである。
敵の鏡に自分が移ることと、自分の鏡に敵が写ること、それは二つのように見えるが根は同じものである。
理屈として語るなら確かにその通りだ。
しかし、いざそれを所作として表そうとすると、知恵や分別という曇りが心を覆いたちまち土の鏡になり、移っても見えず、写そうとしても写らなくなる。
どれほど言葉巧みに理屈を並べても、所作に表せなければ何の役にも立たない。
理屈というものはそもそも際限がない。
だからこそ理屈を並べるのをやめ、自分の才覚や小賢しさを捨て、ただひたすら稽古に専念することが重要なのだ。
四十五
「先前」ということがある。
「先」とは、事の先に立つことであり、すなわち始まりの心である。
「前」とは、文字どおり前にあることであり、相手に向かう心のことである。
伝承における「先の心」とはすなわち「前の心」でなければならない。
「前」とはまさしく「中道(偏りがなく、調和が取れている状態)」を言うのである。
これについては「面向(五段落目)」のところに詳しく記してある。
たとえば車輪の中心にある「真木(車軸)」のようなものだ。真木は前にならない方向は一つもなく、常に中心にあって十方に応じる。
よく考えてその理にかなうよう修めなければならない。
四十六
「位(技術を超えた品格、境地)」というものは、これがその姿だと定めることができるものではない。
あれこれと言葉で説明しようとすることを捨て、ただ何事にもとらわれず無事であること、それが「位」と呼ばれるものかもしれない。
たとえるなら、曇っている宝石をひたすら磨けばやがて本来の光が現れるようなものだ。
その光が現れた状態を「位」と名付けているのだろう。
宝石を磨くことはすなわち兵法の修行である。
自らの内にある曇りや病を磨き清めていけば、やがて病のない身となる。
そのとき初めて「位」というものの意味を知ることができるのだ。
四十七
「中央」というのは心の中央のことをいう。
右にも偏らず、左にも寄らず、上にも下にも執着せず、もとより敵にも味方にも付かず、太刀にも頼らない。
あらゆる方向へのとらわれを離れて心の中道を歩むことである。形や現象の見えるところを計ろうとするのは、心の中道ではない。中道とは敵と味方が対峙し、太刀を交わすその「間(空間、タイミング)」のことだ。
その間は空っぽで何の実体もない。
この形のない場所を小手先の才覚で推し量ろうとしても、決してできるものではない。
一尺の間にも、あるいは一分、一毛、微塵の中にも、それぞれに「中央」がある。
わずか一瞬の時間にも中央があり、「小さな草の露の一粒一粒にまで月が映る」と詠んだ歌のようなものだ。
ただひたすら、「中央」を取ることが肝要である。
六韜(りくとう)に曰く、
「勝者は両陣の間に在り」と。
四十八
三方を閉じ一方を開ける、という戦法がある。
敵はその開けた一方向へ攻め込もうとするだろう。
もし開けておく一方向がなければ敵を制する術がない。
敵の心がその「開いた一方」に向かいこちらを打つ間もなく、水がじんわりと染み込むよう自然に三方向(塞いでいた方向)が別の三方向(敵の逃げ道を塞ぐ形)へと変化する。これこそが止まることのない動きなのだ。
たとえ隙があると見て敵が討ちかかって来ても、実体がなければ水に浮かぶ瓢箪を押すようなものだ。
四十九
上段や下段の構え、あるいは右や左の構えであっても、力を抜いてぼんやりと構えるのは死身(死に体)であり、力を込めて構えるのも死身である。
力を入れ過ぎず、力を抜き過ぎず、上段へもそのまま、下段へもそのまま、右へも左へも無病の身そのままの形で自然に構えるのである。
また、進みながらむやみに上下左右へ手を出すものではない。手は身を守る楯である。この楯をまず敵の方へ立て、敵の攻撃が体に当たらないようにしながら、体は手に引かれるよう後から進むのだ。
たとえ楯が強く構えに乱れがないといっても、ほんの僅かでも動きに止まる処があれば敵に打たれてしまう。
「研楯」という教えは、この流派の法(教え)の一つである。
敵と真っ向から打ち合う時、攻防は一つであることが重要だ。楯で敵の攻撃を受け流しながら、止まることなくどこまでも進み続けることを道と呼ぶ。
この一つは万方に通じる一つである。
もし敵が位置を変えて打ちかかってくれば当たってしまうだろう。敵が位置を替えて打ってくるのは敵の動きである。その敵の動きに対してそのまま水を流し込むように応じれば、水が吸い込まれて落ちるよう自然に対応できる。
五十
「動きの打ち」というものと、「真の打ち」というものがある。
全身や手の内が縮こまったり、たるんだり、力みすぎたり、または弱々しく打つのはすべて「動きの打ち」である。そのような「動きの打ち」では、そのまま水が流れるように押し砕くことはできない。
「真の打ち」というのはたるみも縮みもなく、地から天を貫いているような自然な姿そのままで打つもので、敵がそれを押し止めようとしても水が漏れるように止めることができない。
静かに触れようとしても燈火の先の炎をつかもうとするようなもので、触れることができないのだ。
五十一
「四方に心を置く」と言う事。
それは 魚を捕るために大きな網を四方に巡らせて引き回すようなものだ。
こちらにも網、あちらにも網がある。 その網とはすなわち兵法の道である。
心はあらゆるものに行き渡っていなければならない。
この網をあまりに急いで引き回すと水面に波が立って魚はかからない。ここで言う魚とは敵のことである。どんな魚でも一匹残らず引き寄せてつかまえることができる。
これはまた「軍の箒」とも言えるだろう。
悪を打ち破り、善をすくい取る心である。それはまさに正しさをもって争いを正す道なのだ。
五十二
身に生じる科(欠点や過ち)は、大きなものであろうと小さなものであろうとその身を破るという点では同じだ。
身の内が少しも緩むことなく、自然な生命力が満ち続いている状態を「活き物」と呼ぶ。
わずかでも緩みがあり、動きに継ぎ目や乱れといった科が生じているものは「死身」と呼ぶ。
その死身のわずかな隙から水が流れ込むように敵が侵入し、本来良いとされる部分まで全て打ち破られてしまう。
たとえば、弓や鉄砲などにわずかな傷があればそこから亀裂が入り込み、残りの良い部分まで役に立たなくなるのと同じである。
五十三
たとえば紙をまっすぐ断とうとして、目に頼り、心を込めて切ろうとしても、「まっすぐにしよう」と意識すればするほどかえって斜めになってしまう。
しかし、「定木」というまっすぐな道具を紙にあてがいそれに従って引けば、「うまく切れないのではないか」といった疑念も起こらず、自然とまっすぐに切れる。
兵法においても同じである。
まず自らの身を正しく整え、師の教えを用い、本来の五体そのままを基準とした定木を作り上げることが重要である。
その定木を基準として教えの道を違えず行えば、立っても座っても、前後左右雨のような攻撃があっても、紙を断つ定木のようにどの方向に対しても角が背くことはない。
この定木によって五体の動きを正しく整えることが兵法の道である。
五十四
「付きの身」という事。
敵の太刀に付こうとして付かず、付くべきではないと考えて付かない、ただ自分の心次第である。
重要なことは道から離れずしっかりと付くことである。
敵にしっかり付こうとすれば、かえって離れてしまうのが道理である。
敵に強く太刀を押さえられ、そこから挽回しようとするあまり心の道を見失い、敵の動きに引きずられ、こちらを求め、あちらを外れ、慌てふためき、迷い惑うのは、教えに基づく自からの道に付いていないからである。
古い言葉に「道は一瞬たりとも離れてはならない。離れてしまうものは道ではない。」とある。
五十五
敵に誘い出されて心も身も飛び出してしまう、という病がある。
心が驚くのは身の内いっぱいに心が行き渡っておらず、足りないところがあるからだ。
「心が満ちていること」それがこの流派に伝わる教えである。たとえば暗闇の中に灯火を立て、その光が満遍なく行き渡る様子に似ている。
敵の構えや動きにつられて飛び出してしまうのは、敵を恐れるがゆえに心が先に飛び出し、それに続いて身も飛び出してしまうからだ。
敵に執着せず、ただ自らの身の内をそのままにして動くことが重要である。
敵を圧倒し打ち破ろうと強く攻め立てればかえって敵の勢いに乗じられ、その勢いが自分に跳ね返り、自分自身が苦しむことになる。
また、弱々しく動けば、敵はその弱みにつけ込んで打ち破ってくる。
五十六
柳が風になびく様子に似ている。
その根は足のように土をしっかりとつかみ、性(本質的な性質)が木の枝先まで等しく行き渡り漏れるところがない。
人の身体において中心となるのは腹である。 腹が動かないことこそが大地にあたる。 腹や腰が動いてしまえば、柳の枝先が風になびくような柔らかな動きは生まれない。そうなると自分でも気づかぬうちに所作が途切れ、動きが止まってしまう。
五十七
「遠山」とは上段の中心から斜に通る太刀筋のことである。
右肩の付け根が目付けの位置だが、これは漠然と意識するものではない。身体の備えが向かうところである。 なぜなら打ち出すときに遠山と右肩の付け根が一致するからだ。
敵の太刀が上下左右どの位置にあろうとも、最終的におさまるところは鳩尾(中央を取る)である。
五十八
「有る、無い」と二つを疑い迷う心は刹那も離れることがない。
このように「どちらにも決められず迷う」という病は強い意志をもって治すことが肝要である。
心が定まらないのは悪いことだ。
たとえば耳で聞くべきことを目で確かめようとし、目をキョロキョロさせるようなものである。
多くの人にこのような病があるのではないだろうか。よく工夫すべきである。
五十九
「そのままの道」というのは、天から与えられた本性そのままの体を指す。
敵と向かい合った時、不動不変の心と体で敵をそのまま打ち負かすこと、それはまるで飛び火のようなものである。その飛び火が来る瞬間に形を転じ、心を巡らせることはいかなる神妙をもってしてもできはしない。
敵をそのまま討つ時、自分はそのままで当たらないことを「一の道」と呼ぶ。この一の道はどこまでも途切れることなく続いていくのだ。敵がさらに二へと変化して打ってくるのは敵の変動である。その変動する動きに対して自分はそのままの道を行けば、水が割れ目に流れ込み引き裂いていくように対応できる。
敵がその勢いの過半を上に延び討ってきたり、過半を下に沈んで打ってくるのは敵の「角外(道理から外れた)」の動きである。
そのような動きを打ち砕くことはなおさら自由自在にできる。
六十
「小利大損(しょうりだいそん)」ということがある。
敵がひらりと上を打つと見せかければ、そのわずかな利点である一方向(敵の誘い)に心が引きつけられ、残りの九方は闇となる。しかもその一方向である上段の攻撃も当たり、その後に来る下段の攻撃も当たってしまうだろう。
利も損も考えず、そのわずかな利点である一方向に心が惹かれなければ、十方向全てが明るく見える。
ただ時々刻々その瞬間に我が身ひとり立ち上げ見極めよ、今の今を行くより道はなし。
六十一
ある人は、
「真剣勝負の場においては剣術の習いがある者もない者もただ同じく思慮や分別を超え、敵を打ち倒そうとする心しかない。
斬るにせよ斬らぬにせよ極限の状態に至れば志に差はない。
しかしながら勝敗の是非は日々の習いによって身についた徳や癖のようなものであり、 自分でも知らぬうちにその時に現れてくるものである。
勝ち負けがあるとしても、志においては功も不功も差はない。」と言う。
この理は理解しがたく、勝つか負けるかその結果の良し悪しは運頼りになる。
真剣勝負の場において大切なのは「心が正しい状態であるか」を知る事である。
「無心」といっても二種類ある。
一つは剣術の稽古を重ねた末無心に至ること。
もう一つは敵と打ち結び生死の境に追い詰められ、事に呑まれた結果無心になることである。
それは生木と朽木のように異なるものであり、 我が目指すべき無心は後者ではない。
六十二
「行くに虎あり、帰るに龍あり、立てば焰が生ず」という仏語がある。
思うにこの流派の剣術をひとり楽しむ境地に至れば、たとえ龍や虎の口の中に入るような状況であっても楽しむ心が持てるのだ。
この楽しみ、遊ぶ心がなければ、敵の剣のただ中へなんの迷いもなく踏み入ることは難しいであろう。
六十三
我が内には「自分自身を滅ぼす悪」と「善」がある。
悪は善に対して負けやすいものである。
にもかかわらず、この負けやすい悪を頼り、悪を我が大将とするがゆえに我が内の善も悪と共に滅びてしまうのだ。
敵の善によって追われるのであれば、その隠れ家もあるだろう。
善も悪も我が内にあるがゆえに、山の奥、水の底に隠れても悪を滅ぼす敵が来ないということはない。
恐るべし、恐るべし。


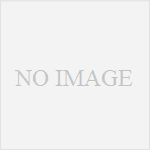
コメント